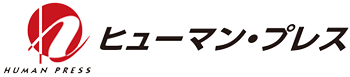発達障害の不思議な世界~その理解と評価から導く最適な指導法
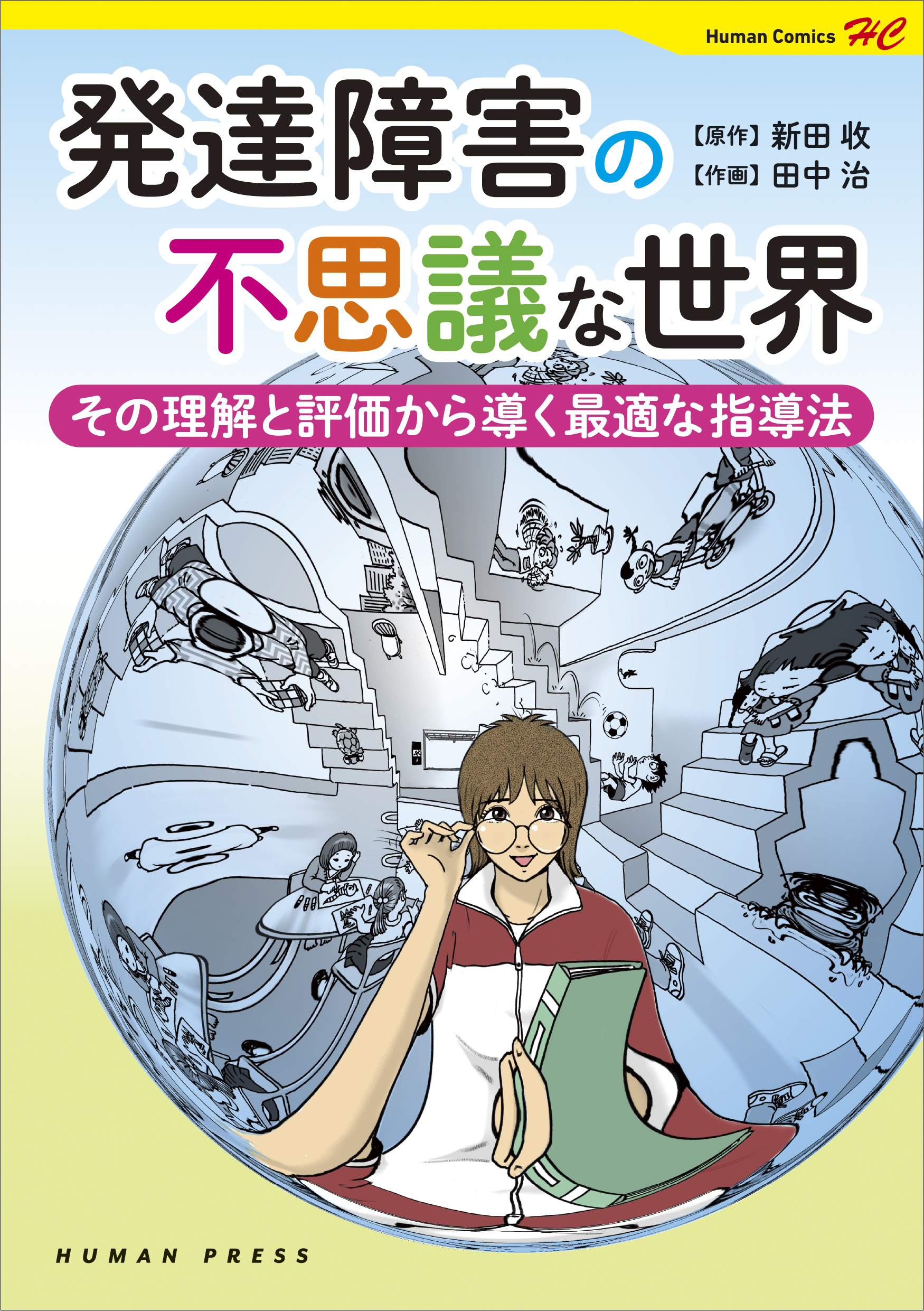
- 原作
- :新田 收
- 作画
- :田中 治
- ページ数
- :208頁
- 判型
- :A5判 1色
- ISBN
- :978-4-908933-31-8
- 定価
- :2,860円(本体2,600円+税)
- 発行年
- :2021年4月
(送料無料)
内容
マンガ感覚で難しい内容もスラスラ学べる新しい学術書!!
子どもの時だけでなく、大人になってから目立つようになり、その症状に悩み苦しむ発達障害。ここ数年、この言葉が医療の枠を超えて一般社会でも、よく話題に上がる。実際に、発達障害と診断される数は右肩上がりである。なぜ、21世紀に入りこのような状況なったのか、その解決策はあるのか。それには、障害への理解が欠かせない。 本書は、発達障害に関する多くの情報から必要な事柄のみを取捨選択し、マンガを適宜用いることで簡単・簡潔に『発達障害の世界』をイメージすることが可能である。難しい専門的な内容や用語などは、一般の人でも分かる平易な言葉や解説に置き換え、スムーズに読めるよう工夫している。そして、自閉症スペクトラム障害(ASD)、注意欠如・多動性障害(ADHD)、限局的学習障害、発達性協調運動障害といった発達障害4疾患に対して、3つのキーワード(症状の原因・特徴・評価)から問題を導き出し、子どもが馴染みやすい遊びや運動を通して、コミュニケーションあるいは社会性の向上を叶えるアプローチ法を説明した。発達障害に関わる人たちにとって、理論と実践が容易に学べる希望の一冊である。
目次
出演者プロフィール
レクチャーⅠ 発達障害とはどのような障害でしょうか
- ・発達障害はいつごろから認識されたのでしょうか
- ・どのように発達障害は定義されているのでしょうか
- ・コミュニケーションの苦手な子どもがいます~自閉症スペクトラム障害の特徴
- ・落ち着きがない子どもがいます~注意欠如・多動性障害の特徴
- ・特定の科目が苦手な子どもがいます~限局的学習障害の特徴
- ・極端に不器用な子どもがいます~発達性協調運動障害の特徴
- ・隣接して重なりあう4疾患
- ・発達障害と妊娠・出産には関連性があるのでしょうか~低出生体重児と発達障害
レクチャーⅡ 発達障害の子どもは世界をどのように感じているのでしょうか
- ・発達障害の子どもは強烈な刺激の中で生活しています
- ・感覚は成長に伴いどのように変化するのでしょうか
- ・環境からの刺激が受け入れられるのは、いつごろでしょうか
- ・感覚は脳でどのように捉えているのでしょうか~皮膚感覚と脳に住む小人
- ・発達障害の子どもにみられる感覚異常は、どのようなものでしょうか
- ・共感覚という言葉を知っていますか~不思議な感覚センサー
- ・人混みの中でも会話ができる不思議さ~選択的注意の重要性
- ・最新の知見でわかった脳機能とは~神経細胞ネットワークの誤接続
レクチャーⅢ 発達障害の子どもに不良姿勢が多いのはなぜだろう
- ・良い姿勢とはどのような姿勢でしょうか
- ・体幹の筋は、どのように姿勢と関わっているのでしょうか~深部筋と表在筋の協調性
- ・スムーズな運動を可能にしているのは、どこでしょうか~小脳の大切さ
- ・発達障害をもつ子どもの姿勢とその原因とは、何でしょうか
- ・発達障害の子どもに偏平足が多いのは、なぜでしょうか
- ・関節のやわらかさは、どこからくるのでしょうか~幽霊はヨガは得意⁉/li>
- ・発達障害の子どもは平衡感覚にも異常がみられます~姿勢の制御に必要なバランス感覚
- ・達障害の子どもは転びやすい~歩行に必要なバランス感覚
レクチャーⅣ 動作のぎこちなさは運動イメージの未熟さが原因
- ・運動イメージとは何でしょうか
- ・イメージトレーニング問題の最終的な姿勢はA~Eのどれでしょうか
- ・身体の動きを知るセンサーとは
- ・子どもはどのようにして動作をまねるのでしょうか~動作模倣
- ・運動の正確性を保つシステムとは
- ・運動イメージは、どのように構築されるのでしょうか
- ・運動をスムーズに行うために必要なものとは
- ・ルーチンな運動は、どのように獲得されるのか~手続き記憶
レクチャーⅤ 発達障害の子どもは生活空間をどう捉えているのでしょうか
- ・なぜ、よくつまずいたり,ぶつかったりするのでしょうか~空間認知と協調運動
- ・どのように空間を捉えているのでしょうか~目にみえる空間
- ・子どもが理解・把握する空間の広がり方~身の回りの空間
- ・運動は協調性なしでは成り立たない
- ・空間に調和して運動するために必要なこと
レクチャーⅥ 発達障害と思ったらチェックしてみよう
- ・コミュニケーションと協調運動の意外な共通点
- ・姿勢と運動を評価することが、なぜ重要なのでしょうか
- ・子どもの感覚状態を把握しましょう~感覚の評価
- ・姿勢の安定性から子どもの状態を把握しましょう①~姿勢に必要なバランスの評価
- ・姿勢の安定性から子どもの状態を把握しましょう②~運動に必要なバランスの評価
- ・姿勢の安定性から子どもの状態を把握しましょう③~体幹筋の評価
- ・簡単な運動から子どもの状態を把握しましょう~基本的な協調運動の評価
- ・少し複雑な運動から子どもの状態を把握しましょう~応用的な協調運動の評価
- ・運動の模倣から子どもの状態を把握しましょう~運動イメージの評価
レクチャーⅦ 遊びや運動をとおして発達障害を改善しよう
- ・遊ぶ・運動する場所を整えることから始めましょう~環境調整は刺激の抑制・排除と付加が重要
- ・遊ぶ・運動する場所を整えた後、次は子どもの状態を整えましょう~脱感作による刺激への適応
- ・すべての環境を整えた後、姿勢がよくなる遊びや運動を行いましょう
- ・姿勢がよくなった後、次は運動中のバランスをよくしよう
- ・姿勢や運動の安定には関節の可動性を安定させることも大切です
- ・さらなる成長を目指し,運動イメージを育てましょう
- ・最後に一連の動きが必要な遊び・運動で全身の協調性を高めよう
- ・効果的な遊び・運動の進め方
レクチャーⅧ 発達障害の悩み相談室
- ・子どもが音に敏感で,パニックなることがあります。どうしたらよいですか
- ・家では,落ち着いて会話ができるのですが,街へ出ると混乱してしまい,会話が成り立たず,突然走り出すや,うずくまってしまうことがあります。どうしたらよいでしょうか
- ・遊びなどの物事の切り替えが苦手で暴れることがよくあります。どうしたらよいですか
- ・いつも家の中を走り回り,食事の時も体を動かしているのですが、どうしたらよいでしょうか
- ・子どもが心配な時,どのような機関に相談したらよいでしょうか
- ・小学生になっても椅子に座るのが苦手です。どのような椅子を選んだらよいでしょうか
- ・運動が苦手で,その時間になると教室から出ていこうとします。どうしたらよいでしょうか
- ・こだわりが強く,食事に関しても決まったものばかり食べます。他の食材も食べるようにしたいのですが,どうしたらよいでしょうか